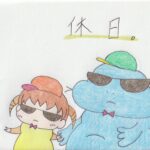過去問で受験勉強

以前の記事では、幅広く英語学習を進めるうえで、過去問が役立つことを記述しました。今回は、まさに、過去問の正当な使い方である、受験勉強においてどのように活用したら良いか、というテーマです。
なぜ今このテーマなのかというと、全国的に再び感染者が増えてきているという現状から、さらには経済状態の悪化ものあり、塾や家庭教師をつける、という勉強方法ではなく、学校教育と独学で何とかならないか、、、
そう考えている方は増えているのではないか、と思います。
なので一般的な勉強法として、よくいわれる基本的な事柄についてまとめてみました。(^^♪

3回は必ずやる
過去問を購入したときに、学校の先生や塾の先生に必ずと言っていいほど言われることです。
取り組む前は、3回ぐらいだったら楽勝でできそうな感じがするのですが、これがしっかりできる人が意外と少ないように思います。
基本としては、過去5年間分を3回やる、ということです。各受験科目ごとに3回、ということなので、
例えば、3科目受験なら、3科目×5年分×3回
5科目受験なら、5科目×5年分×3回
ということなので、思った以上にボリューム感があります。
しかも第1志望も含めて、複数校受験する場合、その学校ごとに過去問に取り組むと、さらにボリュームは増します。(*´ω`*)
それでも、この壁を乗り越えることができた人は確実に力が付いているはずです。
最新のものから順にさかのぼって解いていく
まず初めに、1番最新のものを、時間を実際に測りながら解いていきます。
ひとまずはお手並み拝見ということですね。(#^^#)
現状の実力を知る、という面で大切なステップですが、それだけでなく、時間を測ることで、本番の緊張感をまず体感するということ、そして時間配分の仕方を体に叩き込む必要があります。配点が明記されているものに関してはきちんと採点し、今の現状と向き合うようにしましょう。
一般的に、過去問は古いものになるほど、難易度が上がる、と言われています。
なので、同じ問題を連続で3回ずつやる、という方法で、3回やるのではなく、段々と難易度を上げていく、という意味で新しいものから古い年度のものにさかのぼって解いていくのがおすすめです。
そしてこの時にやっつけ仕事で、とりあえず時間を測ってどんどんやっていってしまいそうですが、忘れないでほしいのが、解説をしっかり読んでなぜその答えになるのか、同じ間違いを繰り返さないようにする、ということです。解きっぱなしになるのが1番もったいないのです。
どうせ3回やるし。。。(*´ω`*)
ではなく。毎回採点をし、次回採点したときには、前回を絶対に超えるぞ、という意気込みを持って取り組みます。
5年分の1巡目が終わった時に気をつけたいのが、一番最新のものは今度はひとまず置いておいて、その前の年のものから(つまり2年前のものから)順に5年前まで、4年分をさかのぼることです。
3巡目に関しても同様です。最新のものはやらずに残しておきます。
最新の過去問は入試の直前にやる
最新のものをあえて残しておく理由はここにあります。
この方法に関しては、賛否両論あるので、これが唯一の正しい方法ではありませんが、1つの選択肢としてここで提案したいと思います。
なぜ最新のものを入試の直前にするのか。
それは今手に入る1番直近の過去問ということになるので、1番本番の入試の形式に近いものであるということです。5年前の過去問、となると、問題の形式や出題範囲が少し異なる場合があります。
そして、本番に備えてメンタルを整える、という意味もあります。解いた順番でいうと、1番初めに1度は解いたものなので、その時に自分が何点だったのか、というデータは残っていることになります。さらには、問題を薄っすら覚えているという点で1度目に解いた時よりも有利な状態にあると言えます。直前に解いたものの方が明らかに点数は上がっているはずなので、
自分はこれだけ成長した!
できるようになった!
と思えるようになります。前回の記憶がいい感じに「薄っすら」だと思うので、覚えているほどやりこんでいるわけではない、ということも最終確認の腕試しとしてはちょうど良いと言えます。
もちろん、受験勉強において、過去問さえやっていればいいというわけではありません。そもそも過去問を解けるだけの実力をまずはつける必要があります。
それでも受験と過去問は切っても切れないので、今回は過去問にフィーチャーしました。
勉強の他の面でもそうですが、当たり前のこと、地道なことをどれだけコツコツできるかというのは、本当に大きな割合を占めます。
勉強を他人が教えることはできても、勉強を実際にするのは本人なので、できない自分を認めることやできるように努力していくことができるかどうか、結局のところ、自分と向き合う、まさに「自分との闘い」といえる分野になるでしょう。
[ad01]