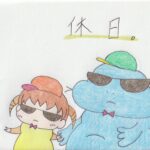北海道と関西のコミュニケーションの違い

仕事の場面でも、日常生活でも、人とのコミュニケーションはできるだけ円滑に進めたいものです。
日々つっこまずにはいられない関西人。つっこまれたくない道民。。。
つっこまずして、どうやって相手との距離を縮め、上手くやっていくことができるのか。
…個人的に北海道に移住して驚いたことの一つに、気候よりも方言や習慣よりも何よりも会話の仕方、コミュニケーションに対する考え方が根本的に違う!ということがあります。
同じ言葉でも受け取り方がかなり変わってしまうことがあるので、同じ日本語を話していてもこちらの意図が伝わらない、根本的なマインド・考え方が違う、、、まさに外国語だと感じることが多くあります。
今回はそんな個人的に経験した戸惑いから学んだこと、感じたことをまとめていきたいと思います。北海道民、もしくは北海道出身の方と意思疎通を図りたいと思っている方々、現在進行中でお悩みの方々の参考になれば嬉しいです。
またあくまでも、関西人の傾向、北海道民の傾向のお話をしているのであって、すべての人がそうだと決めつけているわけではありませんし、どちらかの考え方を否定しているわけではありません。それぞれの視点の考え方を考察することでお互いが変にぶつかり合うのではなく、穏やかに暮らせていけたらいいなと思っています。
北海道民の「つっこまない」マインド
①つっこみ・いじりは道民にとっては攻撃・批判・悪口になってしまう
まず、しばらく暮らしてみて感じたことは、北海道において、つっこむことにはデメリットしかない、ということです。
愛のあるいじり、愛のあるつっこみ。これらのものは基本通じないものだと考える必要があります。そして相手との距離を縮めるつもりでつっこむと鬼スベリします。そして何とも言えない空気が流れます。本気で怒っていると思われてなだめられるか、めっちゃ悪口を言っていると思われるか、めっちゃ文句を言っているように思わえれるか…いずれにしてもこちらの意図していたのとはまるで違う感じになります。
これはボケても同じ現象が起こります。誰にも回収されず、つっこみ待ちのまま鬼スベリするか、真に受けられて真剣に慰められるかのどちらかです。いずれにしても何とも言えない空気が流れます。。。
でもそこは関西人。つっこんでもダメ。ボケてもダメ。となるとどうしたら相手との距離を縮め、本音を引き出せるのか、途方に暮れてしまいます。
そもそも北海道民はなぜ会話をする時につっこまないのか。
「これおかしいと思いませんでしたか?」とか「これ○○やん!ってなりませんでしたか?」と聞くと、結構な確率で返ってくるのは「そんなこと考えたこともなかった」という答えです。
つまりシンプルに疑問に思わない、のです。そして、今こういう状態だと結果こうなってしまう、みたいな先を見据えた話はあまり伝わらないようにも感じます。これは刻一刻と変わりやすい北海道の気候や天気とも関係しているのかなとも感じます。
そのため、もはやつっこみ待ちとしか思えない状況がごろごろと転がっていることが多々あります。もう触れずにはいられない、スルーできない場面です。それでも必ずしもつっこまれるのを待っているわけではない、というのを経験を通して学びました。
②会話のテンポ・話のオチは気にしていない
そもそも人との会話を楽しむ、という文化があまりないように感じます。それは知らない人同士のコミュニケーションにも当てはまるかな、と思います。
なので、急に話しかけると、ものすんごくびっくりされます。例えば、この人道に迷ってるなと思って、「どこ行かはるんですか?どこかお探しですか?」と聞いても驚かれ、何か工事していて交通整理をしているおっちゃんに「何が建つんですか?」と聞いても、「えっっ・・・!?」という反応が返ってきてドン引きされてしまったことがあります。驚かせるつもりはなく、別に相手を困らせようとか責める意図は全くないです。相手がどこに行きたいのか、何が建つのかをしつこく聞き出そうとか聞きたいという意図もありません。軽い気持ちの深い意図はない会話ですが、会話そのものに対する感覚というか重みが違うのかなという印象を受けました。
知っている人同士の会話だとどうかな、と思うと会話を弾ませるのが難しいなと感じます。会話のスピード・テンポはゆっくりで、結論があるようなないような話が多く、結局何が言いたいのか、何をしてほしいのか、見えてこないことも多いです。これは大事にしているものが違うのかなと感じます。
関西人の傾向としては、何か話をする時にいったん頭の中で1つのエピソードとして作り上げて、オチまでつけて、いらん部分はテンポや尺を考えてはしょって(省いて)話す、いかに相手を楽しませ、笑ってもらうか、というのが無意識のうちにあるかと思います。そういう意味では関西人は自分の話をきいてほしいというよりも、相手に楽しんでほしい、エンターテイメントな部分があるのかなと思います。話の内容がどうかというよりも会話のラリーを楽しんだり、その場の空気間を楽しんだり、という具合です。つっこみという「合いの手」や笑いによってコミュニケーションが成り立つという感覚です。
それに対して北海道民は話をする、となった時に過程をすべて話す傾向にあるように感じます。会話のキャッチボールとか短い会話のラリーを繰り返すというよりも、長い語り、という印象を受けます。一見すると話が長くて、もうちょっと頭の中でまとめてから話せばよいのに、と思いますが、これは「自分の気持ちや感情を共有する」ということに重きを置いているのではないかと思います。結論や結果ではなくて、ただ自分の気持ちを言えた、共有できた、そこに満足感とか楽しかったという感情が生まれるのかなと個人的には感じました。
なので、しゃべる時としゃべらない時の差は激しいかなと思います。おとなしい、無口な人が多い印象ですが、いったん話す、というスイッチが入ってしまうと話す、という感じです。
③会話よりも体験を大事にする
「体験」というと少し大げさな感じがしますが、例えば友達とご飯に行くことになった場合、友達と会うことと何を食べるのかではどちらがより重要なのか、ということです。個人的な感覚と経験に基づくものなのであくまでも全員がそうだと決めつけたいわけではありませんが…
確かに「前から気になっていたあのお店に行こう」みたいな明確な目的がある場合もありますが、とりあえずどこかで待ち合わせしてから考える?となる場合の方が個人的には多いような気もします。友達が家に遊びにくる場合も用意するお茶菓子やご飯にそこまでこだわらないかなとも思います。それよりも友達と会うことやそこでの会話、一緒にいる時間が心地よいかどうかの方が個人的には大事かなと感じています。
ただ会話を楽しむという文化があまりない北海道民にとっては、会話よりもそこで同じ体験をする、同じものを食べる、体験を共有することの方が大事なのかなという印象を受けました。私としては会話が弾んでいる感じもせず、何とか面白い話をしてみようとするも若干スベり、大丈夫だったかな、楽しかったのかな、と思う場面に何度か出くわしましたが、後から話しかけてみるとあの時楽しかったねと言われることがあるので少しびっくりすることがあります。そして楽しかったね、の後に「おいしかったね」と言われる確率も高いことに気づきました。同じ空間の中で同じ体験を共有することに価値があるんだな、と思いました。
結論
同じ日本であったとしても、同じ日本語という言語であったとしても、シンプルに価値観が違う、ということです。どちらが良いとか悪いではなく、シンプルに考え方が違う、ということです。会話をキャッチボールととらえチーム意識のようなものがある関西人と、自分の考え、感情、体験を共有したい北海道民。コミュニケーションの取り方に多少のとまどいを感じることもありますが、とまどいやギャップをどう埋めていくか、どう上手に付き合っていくか、引き続き試行錯誤していきたいと思います。